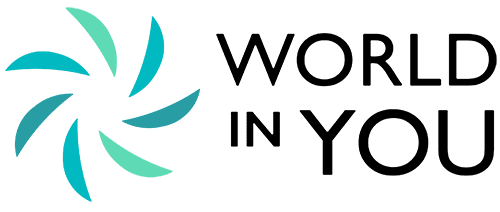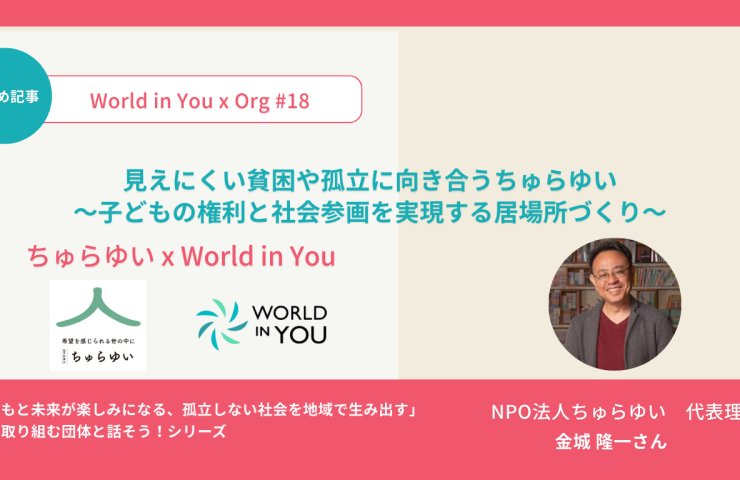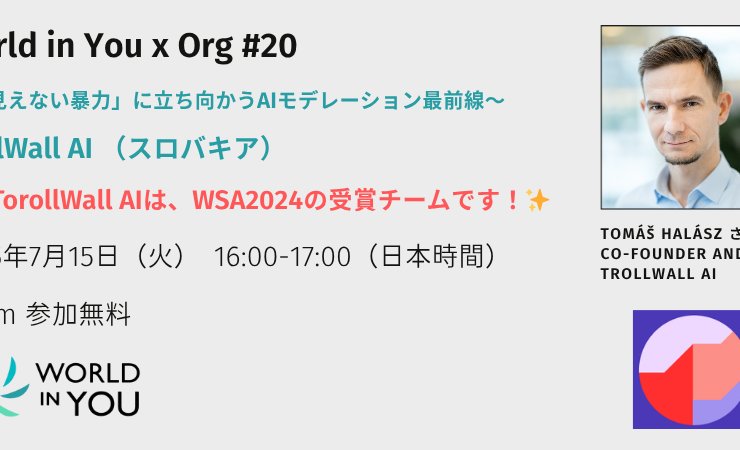【イベント開催報告】「サステナブル経営を実現する戦略的社会貢献とは? ~ 社会課題解決と企業価値向上の両立を目指して」〜 ETIC. / World in You 共催特別セッション

ETICとWorld in Youの共催で2025年1月20日、六本木にて開催されたセッションー「サステナブル経営を実現する戦略的社会貢献とは?- 社会課題解決と企業価値向上の両立を目指して」のレポートをお届けします。
本セッションは、2024年6月に開催した「欧州企業はどのように社員のボランティアや社会活動の機会をつくり出しているのか?」、9月に開催した「社員ボランティアのすそ野を広げるための次の一手は?」に続く第3弾として開かれ、企業のCSR、サステナビリティ、DEI担当の方々を中心に、企業の社会貢献や社員ボランティア、エンゲージメントについて課題や実践について話し合うコミュニティが生まれつつあります。
登壇者として、サントリーホールディングス株式会社CSR推進部長の一木典子さんと、株式会社リコーESG戦略部ESGセンター事業推進室長の赤堀久美子さんをお迎えし、企業の戦略的社会貢献活動のあり方について深い議論が交わされました。
現在、企業による社会貢献活動は大きな転換期を迎えています。かつての単なる慈善事業や広報活動としての位置づけから、経営戦略の重要な柱として捉え直されるようになってきました。特にESG経営が進展する中で、本業を通じた価値創造(CSV)は多くの企業が目指す理想となっています。しかし、その実現には様々な課題があり、多くの企業が事業化の難しさに直面しているのが現状です。
本セッションは、このような背景のもと、戦略的な社会貢献活動のあり方と、それが企業にもたらす価値について探求することを目的として開催されました。
セッションの前半では、両氏から各社の取り組みについての事例紹介や、両氏の課題意識を伺いました。
赤堀さん
- 赤堀さんは、リコー入社後、一度国際協力NGOに転職後、リコーに再入社。戦略的CSR、BOP、CSV、SDGs、ESGなどサステナビリティの推進に、16年間携わってこられた。「社会にインパクトをもたらす企業の在り方の探究」、「社会にアンテナを立て、行動する人を増やす」をマイパーパスとして、大学院での研究もしてこられた。
- リコーでは、「”はたらく”に歓びを」という企業理念に基づき、社会貢献の重点分野の一つに「はたらく人のインクルージョン」を掲げている。17人に1人いる「はたらく」に困難を抱える若者支援の取り組みで、デジタルスキルの習得を通じた就労支援プログラムを展開している。
- 若者支援プログラムでは、社員がプロボノとして参加する支援体制を構築しており、これまで約200名の社員がサポートに加わり、社員の社会貢献意識の向上にも寄与している。
一木さん
- 3年前にサントリーに入り、CSR担当を担当している。その前はJR東日本におり、個人的にソーシャルな活動は続けてきた。
- サントリーで特徴的なのは、「『人間の生命の輝き』をめざす」というパーパスを多くの社員が様々な場面で語ること。このパーパスや「利益三分主義」に基づいて社会貢献活動も行っている。
- 次世代エンパワメント活動「君は未知数」は、困難に直面する子ども・若者の支援を、特に日本で支援がまだ手薄と言われる「思春期世代」に焦点を当て、NPOとの協働を通じて取り組んでいる。貧困の連鎖を防ぎたいと、体験格差の解消や居場所づくりに取り組んでいる。
- 立上げ後、全国の営業現場や取引先からの反響もあり、社内外の関係人口を意識した社会貢献活動を行っている。子ども食堂支援事業では、飲食店との連携を模索している。単なる社会貢献にとどまらず、実施する飲食店にとっても経済的価値と社会的価値の両立につながる取り組みを目指す。
お二人からの自己紹介や取り組みの共有のあと、課題意識を共有していただきました。
- 赤堀さんの課題意識:サステナビリティが経営戦略に統合され、経営者が率先して語る時代になっている中で、「企業価値向上のためのESG」という文脈が強化され、ESGのリスク対応や財務に繋がる取り組みの優先度が高くなっている。社会貢献の経営における重要度を高めるには、どのように位置づけるべきか?
- 一木さんからのコメント: サントリーでは、サステナビリティ経営(環境、サプライチェーンの人権、責任あるマーケティング等)とCSR(社会貢献、文化関連)で組織が分かれており、それぞれがパーパスの元で自律しながら連携している。創業精神に裏打ちされたパーパスの存在、そしてCSR活動について、経営層と本質的な意義や方針を共有できているところは重要。
- 一木さんの課題意識:コレクティブなインパクトにつなげるため、自社だけで取り組むのではなく、NPOやステークホルダーとの連携・協働や、仕組みづくりを重視にしているが、(受益者に直接接する活動と異なり)わかりにくい面もあるため、共感者を増やすための社内外のコミュニケーションに課題感がある。皆さんはどのような工夫をしているか?また、日本の大企業の社会貢献のあり方が進化していくために必要なことは何か?
- 赤堀さんからのコメント: 経営層が社会課題に向き合う意義を体感していることが重要だと思う。それがある上で、社会課題に接点がある社員を増やしていくことが大事。
セッションの後半では、参加者からの問いかけもベースに、登壇者と対話を重ねました。
そこから見えてきた主なトピックをいくつかご紹介します。
【社会貢献活動の評価と目標設定】
- サントリーでは評価についても探求を重ねている。受益者数や参加企業数などの定量的な指標に加え、特に子どもや若者のメンタルヘルス面に係る効用や損失を定量化するなど、社会的インパクトを可視化していけないか検討している。
- リコーでは、社会課題解決への貢献、ステークホルダーとの関係強化、社会課題に対する当事者意識の高い社員の育成、社員エンゲージメントへの寄与の4つを、社会貢献の目的として、それぞれに社会的な価値と社内価値を含めた評価指標を設定している。
- 一木さんの課題意識:コレクティブなインパクトにつなげるため、自社だけで取り組むのではなく、NPOやステークホルダーとの連携・協働や、仕組みづくりを重視にしているが、(受益者に直接接する活動と異なり)わかりにくい面もあるため、共感者を増やすための社内外のコミュニケーションに課題感がある。皆さんはどのような工夫をしているか?また、日本の大企業の社会貢献のあり方が進化していくために必要なことは何か?
- 両社とも、個社だけで出すインパクトではなく、他企業やNPO等との連携を通じた、コレクティブインパクトの視点を重視している。
【NPOとの協働における重要ポイント】
- 信頼関係の構築が最重要。単なる資金提供者と助成/支援先という関係ではなく、共通のミッションやビジョンを持ったパートナーとして協働することが効果的な社会課題解決につながる。
- サントリーでは、NPOと協働して行う事業開発において、社員を1名出向させるなど、深い関係性構築と実質的な貢献を重視している。
- 活動の持続可能性を確保するため、活動の自立化を見据えた支援設計も重要。
【社内理解の促進と事業部門との連携】
- 社員に対して社会貢献活動への強制的な参加要請は避け、社員の自発的な参加を促すアプローチが効果的。
- 社会貢献活動を通じた社員の成長機会の創出や、本業とのシナジー効果を明確にすることで、事業部門の理解と協力を得やすくなる。
- 経営トップ自ら「営業が稼いでくれるからこそ社会貢献ができる」と社内メッセージを伝えることも、部門間の理解を深めるために大事。
【取引先企業や若い世代の社員との価値共創】
- 取引先企業からのCSR・ESGへの関心が高まっており、社会貢献活動が取引先との関係強化にもつながっている。
- 調査によると、10代・20代では企業が取り組むべき社会課題として「貧困・格差の解消」への支持が高い。この世代は、将来の従業員、顧客、取引先等になっていく層であり、この世代の意識は無視できない。
- 不登校や発達障害など、家族に何らかの困難を経験したことのある社員は少なくないようで、そのような経験を持つ社員にとって、子ども・若者支援などの社会貢献活動は強い共感を呼び、リテンション(定着)にもつながりうる。
【活動のEXIT戦略】
- 社会貢献活動を開始する際には、出口戦略をあらかじめ設定しておくことが重要。
- 活動の自立化に向けたロードマップの作成や、持続可能な運営体制の構築支援が必要。
【今後に向けて】
今回のセッションから、今後の企業の社会貢献活動において重要となるポイントが見えてきました。
- 経営戦略との統合:企業理念や事業戦略との整合性を確保しつつ、経営層の明確なコミットメントを得ること
- ステークホルダーとの協働:NPOとの戦略的パートナーシップ、社員の主体的な参加、取引先との連携強化など
- 社会的インパクトの追求:長期的な視点での成果測定、コレクティブインパクトの実現、持続可能な支援モデルの構築
本セッションを通じて、社会貢献活動を単なる慈善事業ではなく、社会課題の解決と企業価値の向上を両立させる重要な経営戦略として位置づけることの重要性が改めて強調されました。取引先や若手社員との関係性においても、社会貢献活動が新たな価値を生み出す可能性が示唆されました。
一方で、社会貢献活動の評価については、多くの企業が試行錯誤を重ねています。次回のセッションでは、ここに焦点をあてていく予定です。詳細は追ってご案内させていただきます。お楽しみに!
◆ゲストスピーカー:
一木典子さん
サントリーホールディングス株式会社 CSR推進部長
 大学卒業後、JR 東日本に入社。八重洲開発プロジェクト、東北エリアの地域活性化などを経て、2022 年サントリーホールディングス株式会社に入社。 「人と自然と響きあい、豊かな生活文化を創造し、人間の生命の輝きをめざし」、同社の利益三分主義に基づくCSR活動を担う。2023年には困難に直面する子ども・若者を支援する次世代エンパワメント活動「君は未知数」を立ち上げ推進している。
大学卒業後、JR 東日本に入社。八重洲開発プロジェクト、東北エリアの地域活性化などを経て、2022 年サントリーホールディングス株式会社に入社。 「人と自然と響きあい、豊かな生活文化を創造し、人間の生命の輝きをめざし」、同社の利益三分主義に基づくCSR活動を担う。2023年には困難に直面する子ども・若者を支援する次世代エンパワメント活動「君は未知数」を立ち上げ推進している。
プライベートでは、「こどもの複合体験施設 モリウミアス」(宮城県石巻市)や「ダイアログ・ダイバシティ・ミュージアム」(東京都港区)のアンバサダーも務めている。
赤堀久美子さん
株式会社リコー ESG戦略部 ESGセンター 室長
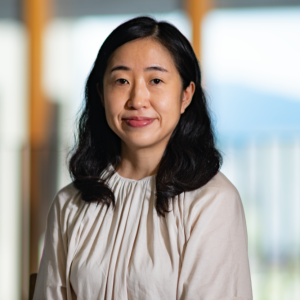 大学卒業後、リコーでの勤務を経て、2003 年国際協力 NGO に転職。イラクに駐在し、学校修復事業に携わった後、東京にて、イラク、アフガニスタンの復興支援等を担当。2008 年、再度リコーに入社し、以来、サステナビリティ部門において、事業を通じた社会課題解決の取り組み、サステナビリティの経営統合・社内浸透等を推進。2021 年からリコージャパンでサステナビリティの推進を担当し、2024 年 4 月より現職。国際協力 NGOセンター(JANIC)理事。2024 年 3 月長野県立大学ソーシャルイノベーション研究科修了。
大学卒業後、リコーでの勤務を経て、2003 年国際協力 NGO に転職。イラクに駐在し、学校修復事業に携わった後、東京にて、イラク、アフガニスタンの復興支援等を担当。2008 年、再度リコーに入社し、以来、サステナビリティ部門において、事業を通じた社会課題解決の取り組み、サステナビリティの経営統合・社内浸透等を推進。2021 年からリコージャパンでサステナビリティの推進を担当し、2024 年 4 月より現職。国際協力 NGOセンター(JANIC)理事。2024 年 3 月長野県立大学ソーシャルイノベーション研究科修了。
◆主催:
特定非営利活動法人エティック
一般社団法人World in You